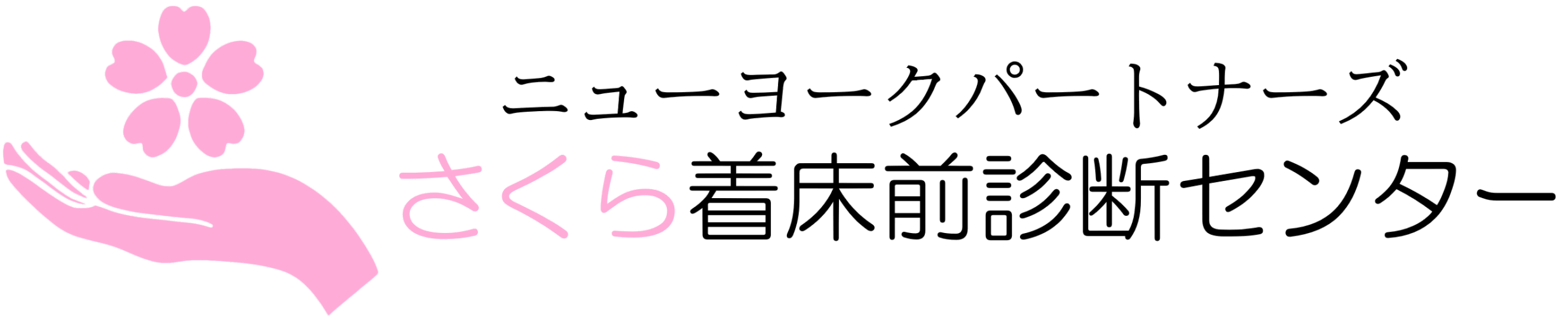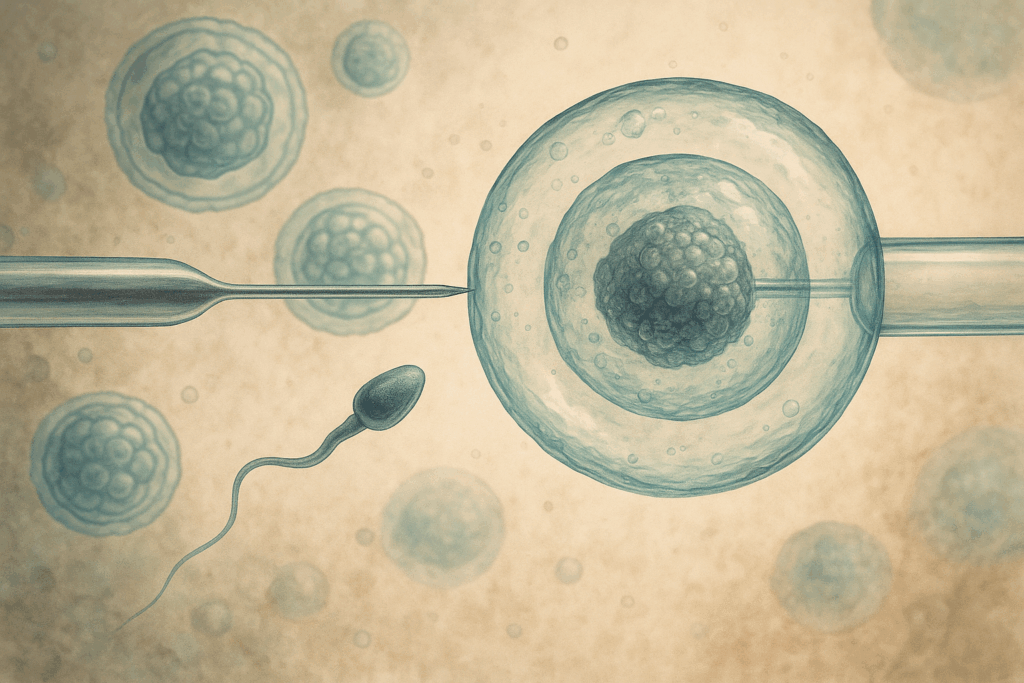米国生殖医療協会(ASRM)の着床前診断委員会による2024年9月発行の染色体異数性に対する着床前診断の有効性についての意見(PGT-a:Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)
米国生殖医療協会(ASRM)の委員会の意見の要点を以下にまとめます。
- 近年、米国において染色体異数性の着床前診断(PGT-a:Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)の実施は着実に増加傾向にあり、23対の染色体の分析技術も急速に進化している。
- 現時点では、米国では全ての不妊治療に対して当検査を標準検査として含める設定は行われていない。
- 染色体異数性の着床前診断(PGT-a:Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)を使用した場合の妊娠、流産における有効性についての研究発表結果は均一でなく明確になっていない。委員会の報告書によると、正確な結論を判断するためには、これらの研究や調査方法は限界があることが事実である。臨床試験が行われている地域、規模(対象人数)、年齢、方法論、着床前診断に使用される技術、個々の患者の状況によって一貫性のない結果が出ているためである。(ニューヨークパートナーズ筆者注釈:これは、技術や診断結果の信頼性を問うものではなく、当診断を使用した場合の不妊治療の結果(着床、流産、出生)に対する有効性に関して議論しているものである)
- 臨床リサーチ数や方法論に限界があるが、染色体異数性の着床前診断(PGT-a:Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)は高年齢の女性(38歳から44歳)で、卵巣能力が良好な場合には有効である可能性がある。
卵子ドナーに対する染色体異数性の着床前診断(PGT-a:Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)
卵子ドナーにはの実施は意味がないという統計が出ている。卵子ドナーのサイクルでは、フレッシュの受精卵移植の方が着床率が高いことが示されているため、受精卵の冷凍を伴う受精卵への生検はネガティブな影響がある。
(ニューヨークパートナーズ筆者注釈:これは別の人間に移植することで、採卵サイクルによってホルモン値があがり移植にそぐわないという条件も鑑みる必要がないためだと考える。フレッシュの受精卵でそのまま移植が可能であることが背景にある)
着床前診断を行った正倍数体の受精卵はひとつのみ移植
米国生殖医療協会(ASRM)は多胎妊娠を減らすために、どの年齢層に対しても正倍数体胚の単胚移植(一つの受精卵)を推奨している。
正倍数体胚の2つの受精卵を移植した場合の多胎妊娠率は65%。2つの未検査胚盤胞の移植の多胎妊娠率は45%。
(ニューヨークパートナーズ筆者注釈:当データを見ると、やはり着床前診断で正倍数体胚が確認できている胚盤胞は妊娠、出生に有効であることを示している)
流産の繰り返し:反復流産、習慣流産
妊娠初期の流産の理由は主に染色体異数性が原因であることがわかっており、染色体異数性の着床前診断(PGT-a:Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)は有効であると考えられる。38歳未満で卵巣能力が低い女性は、標準値をもつ女性と比較し、正倍数体の受精卵を持つ確率が大幅に低いとされる研究結果があり、当着床前診断は有効である可能性がある。
冷凍受精卵移植サイクルについて
現在、米国では染色体異数性の着床前診断(PGT-a:Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)を実施しているほとんどのクリニックにおいては、生検は胚盤胞の受精卵に対して行われている。生検後、冷凍が伴う。言い換えると、ほとんどの正倍数体胚盤胞の受精卵は、“フレッシュ胚移植”ではなく“凍結受精卵サイクル”として移植されている。調査によると、フレッシュでの移植と凍結された受精卵サイクルを比較しても、妊娠率に大差がなかったことから、凍結受精卵サイクルで移植が行われることには問題ないという見解が一般化している。
(ニューヨークパートナーズ筆者注釈:この概念は卵子ドナー使用でなく、自己卵子である場合の同一の患者の想定であるため。当報告書内の前述したドナー卵子において、フレッシュの受精卵はよりよい結果を産むことが発表されているが、通常は患者本人の体外受精サイクルであり、フレッシュでの精卵が良い成績が出るとしても、採卵サイクルによってホルモン値が上がっている同一の患者に移植するというマイナス点と、マイナス要因である“冷凍”とプラス要因であるホルモン値の関係からの“採卵サイクル”とは別の時期の移植サイクルを行う、というプラスマイナスの相殺した成功率が結果的に同等となる、と考える)
生検の日程
胚盤胞になった時点で生検を行うが、6日目に形成された胚盤胞と5日目に形成された胚盤胞とでは、異数性はほぼ同程度であるという結果が発表されている。同様に両者においての生育率もほぼ変わりがない。最近、5日目、6日目までに胚盤胞にならなかった生育の遅い受精卵を、生体ができいなくても破棄せずに、7日目まで培養を実施し生検を行っているクリニックもある。しかし、7日目に胚盤胞期に達した受精卵の異数性のリスクが高いことがわかっており、正倍数性であったとしても着床の可能性が低いと示唆されている。
単一遺伝子疾患のための検査(PGT-M実行)と染色体異数性の着床前診断(PGT-A)の併用
技術の進歩により、同一の標本に対して、単一遺伝子疾患のための着床前診断であるPGT-Mと染色体異数性を検査するPGT-Aを同時に実施することが可能になった。PGT-A実行後のモザイク現象や偽陽性異数性の可能性はあるものの、2つの検査を行うことは効果的であると考えられる。
染色体異数性の着床前診断(PGT-A)を行う場合の冷凍、解凍、生検、冷凍、解凍の繰り返しに関する負担
着床前診断、生検が行われていない凍結保存受精卵に対し、生検を通し着床前診断を希望するケースがある。フレッシュ受精卵に対して生検を行うことが望ましい反面、ある研究では、解凍、生検、(再)ガラス法急速冷凍、(再)解凍の一連の処置では着床率などの大きな結果の違いはなく、悪影響は見られなかった。
染色体異数性の着床前診断(PGT-A)を実施し、結果が確定しない場合が0.86%~3.8%ある、と報告されている。その場合には再度、その標本を解凍、生検、冷凍、と繰り返し行う場合の打撃率に関しては一貫性がない。(2回以上の冷凍、生検の繰り返しは影響がないとする研究と打撃があるという研究結果がある)結論としては、一回の生検は影響が明確でないとしても、複数回の高速冷凍と生検を繰り返す場合は、着床に影響を与える可能性があると考えられる。
男性因子不妊症
精子欠乏症、乏精子症とは、精液内に精子が少ない状態を指し、1ミリリットルに標準では1600万に対し、1500万以下がこの精子欠乏と診断される。この数が乏しい状況は、形態率や運動率にも関連があるとされている。しかし、男性の精子欠乏症と異数性に関する研究や臨床試験データは限られており、現時点では、数少ない研究によると男性因子による異数性の増加と関連性は見られない。
顕微授精(ICSI)の使用
着床前診断を行う場合、顕微授精を使わない従来の授精方法では、遺伝子の汚染リスクが高まる可能性があるという懸念理論が存在するが、この理論は実証されていない。遺伝疾患診断:単一遺伝子疾患の着床前診断であるPGT-Mにおける顕微授精(ICSI)の使用は、出生異常のリスクを増大させないことが分かっている。
民族性
研究データに限りがあるものの、母親の民族性によって異数性率に差は認められない。
着床前診断使用した新生児および小児期への影響
23対の染色体診断:異数性検査の着床前診断(PGT-A)と遺伝疾患診断:単一遺伝子疾患の着床前診断(PGT-M)を受ける理由が違うため、それぞれの患者の生殖能力が違うが、実施されているほとんどの研究では、出産、新生児の時期、小児期において影響がないことを示している。
モザイクについて
通常、細胞は同じ染色体の数を持つ中、モザイク現象とは、ひとつの受精卵内に異なる染色体構成を持ち、正常な細胞と異常な細胞が混在していることをいう。モザイク現象は、PGT-Aで診断される。最近使用されている高性能技術であるNGSではモザイク現象が報告されることが一般的である。モザイクである受精卵は着床し、正倍数体の子孫を生み出すことができるが、着床する確率が低いともいわれている。この臨床については更なる調査が必要とされる。
検査のテクノロジー(技術)について
当初はFISH分析により限られた検査が行われていたが、最近の技術では24のすべての染色体を検査可能となっている。FISHから進歩して、aCGH、qPCRが使用されていたが部分的な異数性やモザイクを検出不可能だった。現在は、NGSとSNPマイクロアレイが主に使用されている。SNPマイクロアレイは、異数性の原因が、精子からか卵子からかを判別し、三倍体と四倍体を高い確率で検出できることで知られている。近年では、NGSが高性能であることから(モザイク検出、PGT-AとPGT-Mの同時検査)多く使用されている。
精度
23対の染色体診断:異数性検査の着床前診断(PGT-A)に関し、正倍数体の受精卵が妊娠に至る確率の研究はなされているが、異数体受精卵の場合の妊娠についての研究が少ない。モザイク、部分的な重複、欠失などの診断が可能になっている今、更なる研究が必要。
生検における受精卵への損傷
一般的に、栄養外胚葉における生検は桑実胚に対する生検より受精卵の生存率の影響は少ないと考えている。これは、栄養外胚葉に対する生検ではより多くの細胞が除去されるものの、ひとつの受精卵内での割合が小さく、胎児になる部分は除去されないからである。桑実胚時期における生検はダメージがある可能性があり、成長中の受精卵に外傷を与え、着床、及び、出産を妨げているというデータがある。しかし、栄養外胚葉生検の影響の研究は多く実行されておらず、着床における栄養外胚葉の重要性を鑑みると、栄養外胚葉を生検することは影響がある可能性もある。
性別選択
23対の染色体診断:異数性検査の着床前診断(PGT-A)の使用により、受精卵の性別を選択する権利を得、選択的な性別選択が可能となっている。米国では、この使用によって男女の性別の均衡が崩れる可能性がある。米国において、性別選択が可能である23対の染色体診断:異数性検査の着床前診断(PGT-A)が行われた場合と、行われない場合とでは、生まれてくる男女比率が大きく違い、男児が上回っていることは懸念すべきだと米国生殖協会は述べている。
完結していない研究
23対の染色体診断:異数性検査の着床前診断(PGT-A)は利点と欠点があるが、研究データが限られている。PGT-A検査は、妊娠中、及び、出産後に検出される異数性のリスクを低減する可能性があるし、異数性によって着床しない可能性や流産を避け、妊娠までの期間を短縮できる可能性がある。また、異数体受精卵を保存し続けることを避けられる、という利点がある。欠点としては、モザイク胚をどう解釈し移植を行うかどうか、という決断に直面する可能性がある。また、着床前診断を行う際、胚盤胞で生体検査を行うが、もし、着床前診断を行わないないとしたら、胚盤胞まで培養、成長を待たずして健康な子供が生まれていた可能性もある。つまり健康な子供になる可能性のある受精卵を排除する可能性がある。
結論
米国では、体外受精治療の中で23対の染色体診断:異数性検査の着床前診断(PGT-A)の使用が増加している。技術も進化しているが、現在は、全不妊治療に行われる一般スクリーニング検査には含まれていない。23対の染色体診断:異数性検査の着床前診断(PGT-A)と、複数ではなく“ひとつ”の受精卵を移植するという併用により出生率が上昇している発表もあり、多胎妊娠の発生率を最小限に抑える方法として有効であることを示唆している。と同時に、最近の2件の臨床試験では、着床前診断を使用してもしなくても妊娠結果は同様であるという結果も出ている。研究は限られていて結論はでておらず、普遍的に不妊治療の一環検査とするまでには至っていない。